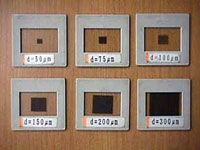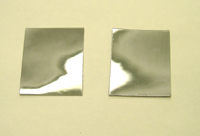装置についているスイッチ 1 (背面にあるかもしれません)をいれればレーザー光が出てきます。
光の量は偏光フィルターや遮光フィルター(プラスチックケースに入っている)を用いて調節します.
実験台によっては絞り 2 で調節できるものもあります.

縦方向の細かい調整には,こちらの方を利用すると便利です.
特に,複数スリットの回折実験では,スリットの選択に微調整が必要になりますが,このダイヤルで調整すれば簡単にできます.
| 光の色 | 波長 |
| 赤 | 632.8 nm |
| 緑 | 543.5 nm |
| 黄色 | 594 nm |
| オレンジ | 612 nm |